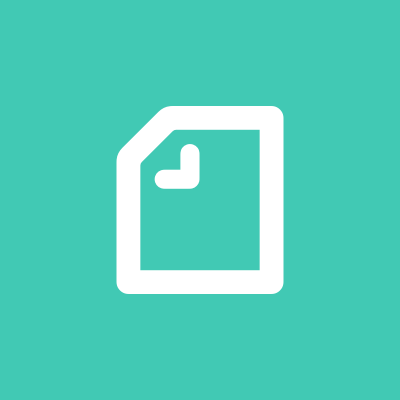今朝、せっかく早起きしたのに、エアコンのタイマーを設定し忘れていた。
日課のストレッチが始められず、部屋が暖まるまでの間、何か本でも読んでいようと、ふと手をとったのが「シェフを『つづける』ということ」(井川直子著)。
イタリアで料理修行した15人のその後の10年を追ったルポルタージュ。
最初に読んだのは、1年半ほど前だろうか。
本を開いたら、ああ、このエピソードを読み返したかったんだ、と気づいた。
函館で「Colz」というレストランを営む、佐藤雄也さんの話。
地に足をつけて生きているシェフという印象だけが強く残っていて、細かい内容は覚えていなかったけれど。
料理の説明には、白樺の樹液、熊笹のブロード、黒文字のスモーク、コクワ酒などがでてくる。
レストランは函館市内にあるそうだが、これらは恐らくレストランから周囲数十キロくらいの範囲で採れるもの。
意外性とか、独自性をという狙いはあまり感じられない。
それは昔からそこにあって、ずっと使われてきたから、僕も使わせてもらっているんです、という自然さがある。
そして、つながりのある信頼できる生産者の食材を使うことが全てに優先するという。
料理ありきで食材を選ぶのではなく、食材ありきで料理を生みだす。
だから、例えば同じ豚肉でも生産者ごとに料理が変わる。
言われてみればあたり前のように思うけれど、本当の意味でそれができるのは、食材と生産者への愛があるからだろうと思う。
どうして、今朝、このエピソードを読みたくなったんだろう、としばらく考えてみる。
この食材でつくるからこれなのだという料理と、この人のためにつくるからこれなのだという料理。
それが同時に実現されたとしたら、とても幸福なことなんじゃないか、と思い至る。
いろいろな要素がカチリとはまった時に起こる、奇跡みたいなことなのかも知れないけど。
でも、それが幸福なことなんだとしたら、ちゃんとイメージを持っておきたい。